
聖書と考古学は矛盾する?鉄器時代(紀元前1200年以降)について聖書の信憑性に迫る
この記事では、旧約聖書に描かれる「鉄器時代」(紀元前1200年以降)の出来事と、考古学・歴史学が明らかにしてきた実際の文化・社会との関係を見ていきます。聖書の記述と考古学が必ずしも対立するわけではなく、むしろ互いを照らし合わせることで「聖書をどう読むか」について理解が深まります。
物理好きの無神論者がキリスト教の牧師になって始めたブログ

この記事では、旧約聖書に描かれる「鉄器時代」(紀元前1200年以降)の出来事と、考古学・歴史学が明らかにしてきた実際の文化・社会との関係を見ていきます。聖書の記述と考古学が必ずしも対立するわけではなく、むしろ互いを照らし合わせることで「聖書をどう読むか」について理解が深まります。

この記事では、主に旧約聖書の最初の方に書かれた出来事の時代(天地創造〜青銅器時代)を対象に、考古学の知見と聖書の記述がどのように重なっている・ズレているかを説明します。それによって、聖書と考古学の関係性・付き合い方・本来あるべき姿を考える一助となればと思います。

今回は、聖書に記されている内容が過去の歴史・考古学の知見とどの程度整合性が取れているか、という視点から聖書の信頼性・信憑性について考えます。また、歴史とは何か・どう読むかという「(聖書を含む)歴史書の読み方の前提」にも光をあてています。
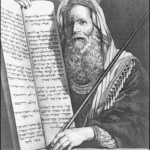
この記事では、「聖書は信頼できる書物か?」という問いに対して、聖書の写本(手写しされた文書)がどのように伝わってきたか、写本にはどんな誤りが入りうるか、そして現存する写本の量と質からどれだけ原文に近づけるかという視点から考えます。
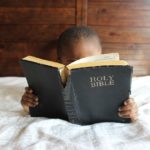
「聖書」は世界中で広く知られ、世界中で既に数十億部も発行されている書物です。そんな聖書とはそもそも「どんな書物」なのかについて、「誰が」「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」「何を」書いたのか――いわゆる5W1Hの視点から整理していきます。

キリスト教にとって、イエス・キリストがなぜ十字架で死んだのかという問いは、教えの中心・中核・核心をなすものです。この記事では、特に「神の正義」「神の愛」「救い」という三つの観点から、イエスの死の理由と意味を大枠で整理します。
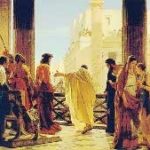
「なぜイエスは殺されたのか」と問われると、多くの人ははっきり答えられないのではないでしょうか。実は、イエスの死にはユダヤ教指導者とローマ帝国総督の思惑も深く関係していました。この記事では、当時の政治的・宗教的な状況をもとに、イエスの十字架刑の裏側にある真実に迫ります。

神様は、人格的に素晴らしい人や優れた功績を挙げた人を優先的に愛するお方ではなく、欠点や弱さのある人も全て愛される恵みに満ちたお方です。神様はこの世の全ての人をありのままで愛してくださっています。その神様の愛と恵みが表されているのがイエスの十字架です。

神様が人を選ぶ基準は才能や能力、知識や経験ではなく、選ばれるに値しない人(選ばれるに値しないと自覚している人)を恵みによって選ばれます。そして神様は、恵みによって選ばれた人といついかなるときも共におられ、その人を通して御自分の救いの御業を成し遂げるお方です。
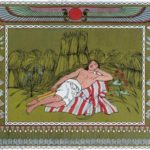
神様が共にいれば問題や困難に遭わなくなる訳ではありません。問題や困難に遭うからといって、突然、神様が共におられなくなった訳でもありません。神様は、私たちが直面する問題や困難を用いて神様の恵みと祝福を広げることができるお方、全知全能で絶対的な主権をもったお方なのです。