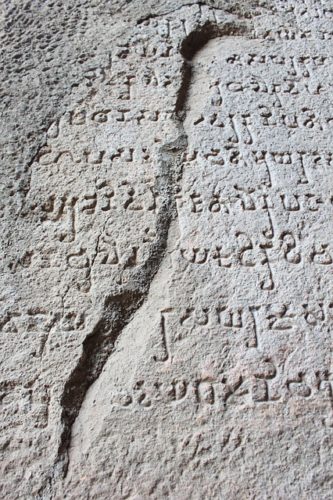
今回は聖書の歴史的・考古学的整合性、つまり
という視点から聖書の信頼性・信憑性について考えます。
ただし、「聖書の信憑性=歴史書として完全に証明されているかどうか」だけを問題にしている訳ではなく、
歴史とは何か?
どう読むか?
という「(聖書を含む)歴史書の読み方の前提」にも光をあてています。
なお、この記事は、過去に掲載した下記の記事の内容から要点を抽出して、キリスト教のことをよく知らない人やキリスト教初心者の方にも分かりやすいかたちになるように、簡潔に要約したダイジェスト版(まとめ)です(内容を加筆修正しているところもあります)。

興味を持たれた方は是非、上記の記事もご一読ください。
「歴史」の性質
歴史の主観性
まず「歴史」のもつ性質について考えます。
辞書的には歴史は「過去の変遷・記録」ですが、過去を知るには「その出来事に関する記録(情報)が後世に残っている」必要があります。
その記録を残す行為自体に、何を残すか選ぶという主観が入り、さらにそれを読む側にも解釈の主観が入るため、
と言っても過言ではありません。
新聞記事でさえ取捨選択の過程で偏りを含むのと同じで、古代の記録(聖書も含む)にも主観が入ります。
ここで重要なのは、
という点です。
科学は実験で再現・検証できます。
それによって、いつでも、どこでも、誰もが確かめられる「客観的な事実(法則)」が確立されていきます。
対して
です。
この過去に起こった出来事は、いつでも、どこでも、誰もが確かめられる訳ではありません。
ですから、
だと言えます。
のが自然ということになります。
これは歴史の読み方・信憑性を考えるときに重要なポイントです。
歴史のメッセージ性
次に、
という性質があります。
のです。
例えば、古代ギリシャの歴史家 ヘロドトスは『歴史』という著作において、自身が収集した地理・社会慣習・伝説・神話などをもとに、ペルシャ戦争という過去の出来事が「なぜ起こったか」を説明しようとしています。
つまり、歴史作品とは
ものとも言えます。従って、
だと言えます。
聖書と歴史的・考古学的整合性
では、このような「歴史/歴史作品」の性質を踏まえて、
聖書をどう読み解くべきか?
聖書に記されている内容が過去の歴史・考古学の知見とどの程度整合性が取れていると言えるのか?
について考えます。
ここで注意したいのは、
という点。
ということです。
従って、聖書を読み解こうとする際の鍵となる問いかけは、「この出来事は本当に起こったか?」よりも、
だと言えます。これはつまり、
ことを意味しています。
とはいえ、聖書記述の歴史的・考古学的信憑性を問うことに意味がない訳ではありません。
少なくとも、以下の二つの理由から、聖書の歴史的・考古学的検証が重要だと言えます。
一つ目は、聖書の作者が「過去のある出来事が実際に起こった」という前提で何かを語っている場合、その前提の信憑性を検証することが「そのメッセージが意味を持つかどうか」を考える上で必要になるからです。
例えば聖書は、イエス・キリストが十字架に架けられ、死んで葬られた後によみがえった(復活した)と主張します。
そして、キリスト教の教えは全て、このイエスの十字架上での死と復活という過去の出来事を前提としています。
ですから、このイエス・キリストの十字架上での死と復活という大前提についての歴史性・信憑性が揺らぐなら、聖書(キリスト教)のメッセージ自体の意味・正当性も揺らぐことになります。1
二つ目は、歴史的・考古学的な検証を通して「作者がどこを脚色しているか/どこを強調しているか/どこを省略しているか」が見えてくるからです。
脚色・強調・省略のパターンを知ることは、作者が何を「重要」としていたか・何を「重要でない」としていたかを知る手がかりになります。
これは聖書のメッセージを理解する上で極めて有益な情報となります。
まとめ
本記事のポイントを整理すると以下になります。
- 「完全に客観的な歴史(過去の出来事のありさま・記録)」というものは、厳密には存在しない。
- 歴史作品(そして聖書)は「過去の出来事を語ることで何かを伝えたい」とする作者の意図・メッセージを含んでいる。
- 「歴史的・考古学的信憑性」は、聖書(歴史作品)の価値・信頼性を決める唯一の基準ではない。
- 聖書を読み解く際の鍵となる問いは、「この出来事は本当に起こったか?」よりも、「この出来事・表現とあの出来事・表現はどうつながっていて、それらを通して筆者は何を言おうとしているのか?」というものである。
- それでも、聖書記述の歴史的・考古学的整合性を検証することは、「作者が過去のある出来事を前提としている」場合、「作者が何を重要だ・重要でないとしているかを見極める」際に有益である。
このように、「聖書は信頼できる書物か?」という問いに答えるには、単に「ある出来事が起こったかどうか?」を問うだけではなく、
ある出来事がどう語られているか?
その出来事を通して何を伝えようとしているか?
を含めて読む視点が不可欠です。
聖書をただ古い歴史書としてだけではなく、メッセージ性を持った文書として読み進める時、より深い理解が得られるでしょう。
